国指定重要無形民族文化財(指定名 磯部の御神田(おみた))
白真名鶴(しろまなづる)の伝説がその起源と伝えられる伊雑宮御田植祭(いざわのみやおたうえまつり)は、千葉の香取神社、大阪の住吉大社とともに日本三大御田植祭の1つに数えられ、磯部に初夏の到来を告げる。
勇壮な男達が大きな団扇のついた忌竹(いみだけ)を奪い合う竹取神事、古式ゆかしい装束に身を包んだ太鼓打ちや簓摺(ささらすり)らによる田楽が響きわたる中、白い着物に赤いたすきがけをした早乙女たちによって厳(おごそ)かに行われる御田植神事、その後、一の鳥居に向けて行われる踊込みと、祭りはいくつもの情景を私たちに見せてくれる。この神事が現在の形になったのは平安時代末期か鎌倉時代初めと伝えられており、より脈々と受け継がれてきた伝統と歴史の積み重ねに生まれた、(そうごん)な時代絵巻が繰り広げられる。(パンフレットより)

※伊雑宮
いざわのみやは、「いぞうぐう」ともいい、伊勢神宮内宮の別宮の中でもとりわけ高い格式を誇る。
白真名鶴(しろまなづる)の伝説
天照大神(あまてらすおおみかみ)にお供えする幸を求めて、倭姫命(やまとひめのみこと)の一行が訪れたとき、一羽の「白真名鶴」が見事な穂を落としたとされ、これを備えて造られた宮が現在の伊雑宮(いざわのみや)だと伝えられています。また、この白真名鶴の霊をまつった「佐見長神社(さみながじんじゃ)」は別名を「穂落宮(ほとしみや)」とも呼ばれ、人々に親しまれています。(パンフレットより)

伊雑宮 御田植祭 タイムスケジュール : 毎年 6月24日
八時十分頃 杁(えぶり)・田道人(たちど)役は「七度半」の使いにたつ。
九時五十分頃 「式三番」を納める。
十時二十分頃 伊雑宮の一ノ鳥居内に整列し、修祓をうける。
十時三十分頃 御正殿に参拝する。
修祓所にて神官より作長が早苗を授かる。
十時四十分頃 伊雑宮より御料田へ参進する。
十時四十分頃 伊雑宮より御料田へ参進する。
十一時頃 御料田に参者する。
作長は左、右、中と早苗を奉下する。
早乙女、田道人(たちど)らは苗代を三周半して早苗を取る。
竹取神事に出る裸男は御料田に入り、苗取りが済むのを待つ。
十一時二十分頃 「竹取り神事」。
十一時三十分頃 「御田植の神事」。
小謡一番から九番がすむと中休みとなり、奉仕者は若布(わかめ)の引張肴で酒宴次いでおくわか、さいわかによる「刺鳥差(さいとりさし)の舞」。
続いて小謡十番から十八番まで唄う。十三時頃終了。
十五時頃 「踊り込み」
御料田から約2時間かけて伊雑宮一ノ鳥居まで練る。
十七時頃 役人一同一ノ鳥居内に整列し、太鼓、簓(ささら)の三人が千秋楽の舞を行い、神事はめでたく終了する。 (※ 磯部の御神田奉仕会より配布された資料より)



伊雑宮より御料田へ参進する。


続いて・・・②御料田に参者するはこちら→★
———————————————————
①伊雑宮御田植祭(いざわのみやおたうえまつり)
②御料田に参者する
③竹取神事 (泥まみれになる裸男たち)
④竹取神事 (忌竹(いみたけ)を奪い合う)
⑤御田植神事 (御料田)
⑥踊込み
⑦千秋楽の仕舞
この記事のライター紹介
 伊勢乃志摩子
伊勢乃志摩子WEBデザイナー&カメラマン&ブロガー&ユーチューバー
住まい:三重県志摩市横山展望台から見える伊勢志摩国立公園の中
高校時代からの趣味は写真📷ウェブサイト制作歴 22年
profile
2000年 ウェブサイト制作事業スタート
2016年 S・O・L・A・R・I・S始動
コマーシャルフォト・ポートレイト撮影
アルバム、フォトブック、パンフレット、名刺など印刷物制作、動画制作、SNS指導もやってます。
気まぐれに地域情報を投稿しています。
取材や掲載希望の方はお問合せフォームよりご連絡ください。お仕事のご依頼も大歓迎です!!
>>お問い合わせ先<<
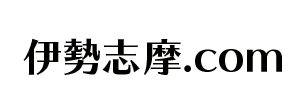

























この記事へのコメントはありません。