平成24年1月11日(400年目)
午後14時より弓引神事が浜島宇氣比神社にて執り行われました。
資料に基づき、撮影した写真でご説明させて頂きます。
・弓引討手 井上 奏 ・ 阪口 匠 (浜島中学二年生)
・盤魚所役 井上 伴大
・魚こなし(介添役) 松尾 泰則
・矢取り 柴原 秀伃
由緒
浜島宇気比神社に古くより伝わる海上安全、大漁満足、家内安全を祈る神事。
先ず神社において祭典を執り行い引き続き夕刻神事を行う。
弓引(討手)は氏子中より二十歳未満未婚の青年二名(長男に限る)を里、大矢、の二地区より選定する。的は大小二個を用い前日に作る。大的は方形(縦横約三尺)、小的は円形(直径約八寸)
式場は宇氣比神社宮域に接続する御田の浜に設けられる。弓引(討手)をはじめ漁業関係者、古老、招待者等の列席者が着席すると必ず「盤の魚」(ばんのうお)と称する行事が行われる。



場の中央に置かれた俎板で手を触れず俎箸を置いて鰡(ぼら)を断ち切り再び元の姿に整える儀式で代々井上家が世襲している。この元の姿に整えられた鰡と残りの一匹を魚こなし役が調理する。

切り身は神事関係者が家に持ち帰り神棚に供え年中の豊漁を祈る慣わしである。

了って酒をくみ列席者は的に向かい座すと続いて「弓引」が行われる。
討手二名は所定の位置に着くと片肌を脱ぎ(介添え役として討手の叔父が控える)先ず大的に向かい、二本づつ交互に三度矢を放つ。次いで小的に同様に矢を放つが最後の1本は海に向かい空高く放つ。了って討手は服装を整え餅と神酒を携え的場に進みこれを供える。
なおこの神事において小的の黒星を討たときには「祝直し(いなおし)と称して翌日引き直しされる慣わしである。
—————————————————————————-
代々井上家が世襲しているこの儀式。400年めの本日 井上伴大さんが
大勢の報道カメラマン、観客を前にしながら相当緊張も高まるとは思いますが
一切手を使わず、断ち切った鰡を再び元の姿に整えられました。
この儀式を目の前で拝見させて頂いた上、鰡の切り身も頂いて帰りました。
志摩にはこんなにも素晴らしい伝統の儀式が400年も続いていることに感動しました。(志摩子)
続きます→★
この記事のライター紹介
 伊勢乃志摩子
伊勢乃志摩子WEBデザイナー&カメラマン&ブロガー&ユーチューバー
住まい:三重県志摩市横山展望台から見える伊勢志摩国立公園の中
高校時代からの趣味は写真📷ウェブサイト制作歴 22年
profile
2000年 ウェブサイト制作事業スタート
2016年 S・O・L・A・R・I・S始動
コマーシャルフォト・ポートレイト撮影
アルバム、フォトブック、パンフレット、名刺など印刷物制作、動画制作、SNS指導もやってます。
気まぐれに地域情報を投稿しています。
取材や掲載希望の方はお問合せフォームよりご連絡ください。お仕事のご依頼も大歓迎です!!
>>お問い合わせ先<<
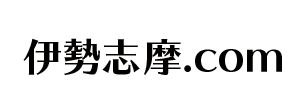

























この記事へのコメントはありません。